安全な住まいとは? 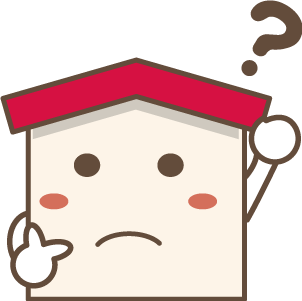
2025年の法改正により”住まいの安全”はどう変わるのか?
本コラムでは、建築基準法の歴史を振り返りながら、住まいの安心と安全をさまざまな角度から考えていきます。
「安心とは、安全とは。」 皆さんも一緒に考えてみませんか?
「四号特例」と”特例”にせざるを得なかった背景
前回のコラムでは、「四号特例」と”特例”にせざるを得なかった背景について解説しました。
<四号特例とは>
- 四号建築物とは、建築基準法第6条第1項の一号~三号に該当しない建築物(比較的小規模な建築物)のこと。
- 特例とは、法6条の4に基づき「建築士が設計を行う四号建築物においては、確認申請時に一定の規定が省略」される制度のこと。
検査(審査)も同様に、建築士である工事監理者が設計図書通りに施工されていることを確認した場合、一定の規定の審査が省略されます。
- 一部の規定の確認や審査が省略される場合でも、規定の確認と審査が免除されるわけではなく、規定を守り「法に適合」すること。
復習になりますが、四号特例とは、建築確認審査を「簡略化」するという規定です。
当時は建築確認審査を行政が担っていましたが、現在は大半を民間の建築確認検査機関が担っています。
「特例」がもたらした弊害
前述のとおり、確認審査業務の合理化は「四号特例」によって補われました。
しかしながら、この特例がもたらしたものには弊害もありました。
■四号特例を巡る経緯
※日本弁護士連合会が四号建築物に対する法規制の是正を求める意見書を公表した記事より引用
<年表>
・1983年(昭和58年)
建築行政職員の不足を理由に、緊急措置として小規模建築物で建築士の設計によるものに対し、四号特例制度が開始された。
・1999年(平成11年)
建築確認の民間開放を軸とした改正建築基準法が施行された。
・2006年(平成18年)
四号特例が適用された分譲戸建住宅で、大量の壁量不足が発覚。これを受け、国土交通省は2009年(平成21年)12月までに
この四号特例を廃止すると発表した。
・2007年(平成19年)
構造計算耐震偽装事件を受け、建築確認申請の厳格化を軸とした改正建築基準法が施行された。
建築確認申請は大混乱に陥り、大きな問題となった。
・2010年(平成22年)
2007年(平成19年)に起きた建築確認の厳格化に伴う混乱を踏まえ、当面、四号特例の継続が発表された。
これにより、四号特例の廃止は撤回となった。
・2014年(平成26年)
社会資本整備審議会建築分科会が、四号特例について引き続き検討すべき課題と位置付けた。
・2018年(平成30年)
日本弁護士連合会が四号建築物に対する法規制の是正を求める意見書を公表。
重大な構造瑕疵が争点となった建築紛争において、特例が建築士の盾となり、建て主側の責任追及や設計瑕疵の立証を
阻んでいたため、日本弁護士連合会は特例の全面撤廃を求めた。
・2020年(令和2年)
改正建築士法の施行により、四号特例を含めた全ての建築物について見直しが行われることとなった。
ここまでの経緯から分かること
年表からも分かるように、「四号特例」の廃止は実務への影響が大きいとして、繰り返し先延ばしにされてきました。
これらの長い経緯を経て、来年の2025年(令和7年)4月、改正基準法施行により規定が改められることとなります。
>>次回は「改正される内容と主旨、改正によるメリット」です。お楽しみに