安全な住まいとは? 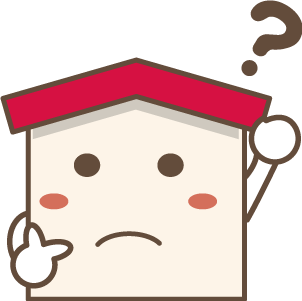
2025年の法改正により”住まいの安全”はどう変わるのか?
本コラムでは、建築基準法の歴史を振り返りながら、住まいの安心と安全をさまざまな角度から考えていきます。
「安心とは、安全とは。」 皆さんも一緒に考えてみませんか?
「特例」がもたらした弊害
前回のコラムでは、四号特例がもたらした弊害について解説しました。
1983年の制度開始から今日までの長い経緯を経て、2025年(令和7年)4月、
四号特例は改正建築基準法の施行により規定が改められることとなります。
改正建築基準法の内容
「脱炭素社会の実現に資するために建築物のエネルギー消費性能の向上に関する
法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」
この改正建築基準法は、令和4年6月17日に公布されました。
<改正内容>
(1)建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
(2)階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安定性の検証法の合理化
(3)中大規模建築物の木造化を促進する防火規定の合理化
(4)部分的な木造化を促進する防火規定の合理化
(5)既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
(6)既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化
【国土交通省HP】
・脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律
(令和4年法律第69号)について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_shoenehou_kijunhou.html
・資料ライブラリ(軸組工法の確認申請・審査マニュアル2024年11月第3版など)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html
改正の主旨
・通常、構造計算を行わず仕様規定に適合させることで構造安全性が確保される小規模の建築物であっても、
伝統的工法等で一部の仕様規定を満たせない場合、高度な構造計算により構造安定性を確認している(第20条第1項第4号ロ)。
・小規模建築物であっても、高度な構造計算により構造安全性を検証した場合、建築確認における構造計算の審査に加え、
構造計算適合性判定による複層的な確認が必要(法第6条の3第1項)。
・高さ13mまたは軒高9mを超える木造建築物を建築する場合、高度な構造計算(許容応力度計算等)により、構造安全性を確認する
必要があり、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない(法第20条第1項第2号)。
・近年の建築物の断熱性向上等のため、階高を高くした建築物のニーズが高まっている。
・一定の耐火性能が求められる木造建築物の規模(第21条第1項)については、安全性の検証の結果、高さ13m超または軒高9m超から、
4階建て以上または高さ16m超に見直されている(平成30年法改正)。
・2014年(平成26年)の豪雪被害をうけ、スパンの大きい等の要件に該当する建築物では、構造計算において積雪荷重を割り増す
ことになっている(平成30年告示改正)。
・2階建以下で延べ面積500㎡以下の木造建築については、大スパンの屋根であっても構造計算が求められていない(法第20条第1項)。
・多様なニーズを背景に、大空間を有する建築物が増加しており、これらの建築物に対応した構造安定性の確保が必要となっている。
改正によるメリット
●省エネ基準への適合
・断熱性能が高くなり、光熱費等を節約できます。また、住まいの長寿命化が図れます(長持ちする家になる)。
・冷暖房費が抑えられ、消費電力を削減することで環境負荷を軽減できます。
●構造・耐震性の向上
・これまで四号特例により建築士に託されていた木造建築の構造審査も、「確認審査」が機能することで改善され、
建築物の欠陥問題を未然に防ぐことが可能になります。
・耐震性能が確保され、耐震性の高い住まいを求めることが可能になります。
以上のように、今回の法改正によって「住まい」は「より安全」になり、大きな安心を得られるようになります。
改正に至った背景を改めて振り返り、安心で安全な住まいづくりに努めていきましょう。
<建築基準法の第1条>
「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」
-Fin-